 
紅の宇宙(くれないのそら)第1部
千年という時を越えて
人は失った歴史を取り戻すことができるのか
時代という大きな流れによって
忘却の縁に封じ込まれた
人類の真なる歴史
民主主義といわれた
人が人として生きることができた時代
青年はすべてを取り戻すため戦う
漆黒の宇宙を
深紅の炎に染めて
プロローグ
宇宙標準暦一五六二年八月一○日、惑星フェリザールの宮殿では豪華な祝宴が開かれていた。この日、クレティナス王国第一五代国王となったアスラール三世の即位を祝ってのことである。
国内外から王族、貴族、高官、高級軍人達が家族を伴って集まり、テーブルいっぱいに並べられた美しい料理を囲み、宮廷楽士の雅びやかな演奏に耳を傾けていた。宮殿の外では、王国の誇る宇宙艦隊による砲声がとどろき、青白い光の帯が夜の空を彩っていた。
美しい金髪とアイスブルーの瞳をたずさえた若き国王アスラール三世は、金糸、銀糸に装飾された赤を基調とするシルクのマントをまとい、人々の中心に座していた。彼のまわりには、王妃レティシア姫をはじめ、宰相ウォンテリュリー、叔父であるヒルファーディング公爵、その妻アゼリアがあり、さらにそのまわりに彼の政権を支える執政リーデンバラス、王国軍司令長官ベルトール元帥、戦略宇宙軍司令長官レーン・ドルト元帥、国防軍司令長官イストリア元帥等がとりかこんで祝いの言葉を述べていた。彼らは皆、アスラール三世が王太子の頃より手足となって、彼の王権の確立を支えてきた者達であった。
このクレティナス王国は、銀河に存在する恒星間国家の中でも、銀河皇帝を擁する千年帝国(銀河帝国)をのぞいては、比肩のしようのない勢力を持つ強国であった。汎銀河的な広がりを持つ人類の精神的な支配者である銀河教皇でさえ、クレティナスには一目を置き、アスラールの即位式には教皇の代理としてバレンヌ大司教を送ってきていた。
しかし、こうした勢力を誇るクレティナス王国も一○年前までは辺境で細々と命脈を保つ小国の一つにすぎなかったのである。絶えず隣国の脅威にさらされ、領土を日ごとに侵食されるという国であった。二○○年以上も戦乱の続く銀河の中ではあまりにも小さな存在だったと言える。
それが、この一○年間で百以上の星系を従える一大恒星間国家に成長していた。人口で二○倍、面積で七○倍とその膨張は著しい。人々は、そのすべての要因をアスラール三世の英明さに求めている。銀河最大の征服者、史上最高の名君、偉大なる英雄王、彼を彩る修飾詞は皆、彼の才能と実績に由来していた。
この年、二八歳になる金髪の若き英雄王は、美の女神に愛されているといっていいほどの美貌を持ち、見る者すべてに強い印象を与えた。すらりとのびて均整のとれた肢体もその美しさを補っている。美貌と才能の二つが最も高い次元で結び付けられたと称してよかった。さらに彼には美しい妻がいた。彼の隣に立って見劣りしない女性など銀河中を捜しても唯一彼の妻をのぞいては存在しない。彼の妻レティシア姫も彼より五つ年下の清楚で可憐な美しい女性であった。二人の並んだ姿を見た者は皆一様に、古代の人々が想像した神と女神の姿を思い浮かべるのだった。
その美しい夫妻は、祝宴の合間をぬって宮殿のバルコニーに足を運び、今にも落ちてきそうな輝きを放つ満天の星空を眺めていた。薄着の肌には少し冷たい夜風が二人の体を洗っていた。
「寒くはないか、レティシア」
「いいえ。こうして星を見ていると何もかも忘れてしまいそうですもの」
つい数刻前、自らの黄金の髪の上に幾多の人々の支配者の象徴である冠をのせていた青年は、妻の声にうなづきながら空を見上げていた。アイスブルーの瞳に星々の光を受けてますます輝きを増している。見る者すべてを魅了するような妖しい瞳であった。
「ああ、星はすべてを忘れさせてくれる」
アスラールは目を細めると視線を彼の愛する美しい妻のほうへ移した。レティシアの長い光沢のある金髪が風になびいていた。
だが……彼には忘れてしまうことのできないものがあった。
「レティシア、余はよくばりな男だ。銀河の五分の一を平らげ、国王の地位につき、そなたまで手に入れたというのに満足していない。……この空に輝く星々すべてをこの手につかまなくては、余の心は満たされないのかもしれない」
レティシアは目をふせた。寂しげな瞳が一瞬だけアスラールに向けられたがレティシアの表情はすぐに普段の彼女に戻っていた。
「アスラール様の使命感がそうさせているのです。わたくしのことはお気になさらずに、アスラール様のやりたいことをなさって下さい」
レティシアは強い女性であった。常に自分のことよりもアスラールのことを優先させていた。それゆえにアスラールは彼女の気持ちが痛いほどわかり、自分の理想、あるいは野心のために彼女を犠牲にしてしまったことを心のどこかで恥じた。しかし、彼は自分に言い聞かせるように言った。
「すまない、レティシア。しかし、今、余がこうしている間にも、あの宇宙は戦いの光にあふれているのだ。二○○年にもおよぶ銀河の混乱は終わってはいない。誰かがこの戦いに終止符を打たなければ……」
アスラールが全部を言いおわる前にレティシアの口が開いた。
「わかっております。ですからアスラール様がお戦いになるのですね。わたくしは、お止めはしません。ここで、アスラール様がただ一刻も早くすべてを手に入れられて、わたくしの許へ戻ってきて下さる日をお待ちしております」
金髪の若き王は、彼の愛する妻の背にしなやかなその腕をそっとまわした。男性にしては少し細い優美な腕だった。その中で、レティシアは全身の力が抜けていくのを感じながら華奢な肢体を彼女の最愛の夫にあずけた。
「約束しよう。必ず銀河を手に入れてそなたの許へ帰ってくると」
アスラールの端麗な唇の震えが止まると、そのままそっとレティシアのやわらかい唇に重ねられた。これが、今彼にできる妻への精一杯の贈り物であった。
銀河の戦いは今も続いている。各地で多くの人の幸せを奪い、傷つけているのだ。戦いの始まりが何だったのか、今となっては知る意味もない。しかし、宇宙には自分の理想を求めて戦う英雄達がきらぼしのごとく存在していた。銀河皇帝ゼリュート、銀河教皇カーザイル、獅子王カセリア、神将タイラー、戦争の天才レオン・ビリュフォンド、そして、英雄王アスラール。この中の誰が銀河を手中に納めるか予言できる者はいない。だが、これらの人物が歴史を創るであろうことは確かであった。
そして……
アスラールは、祝宴の行なわれている広間の方を振り返った。そこには、彼の信頼する部下達が顔をそろえていた。だれもかれも才能あふれる人物達だ。
「余はよい部下達に恵まれている。レティシアの許へ帰れる日もそう遠くはないかも知れない」
アスラールは独りつぶやいた。
空にはまだ美しい星々の光が輝いていた。戦火の光も混じっているのかもしれない。しかし、地上から見上げる者達にとっては美しい夜の光景でしかなかった。その中で、星々の向こうに現在も戦っている彼の部下達がいることを、アスラールは思い出していた。
|
 |
  |
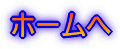
|

